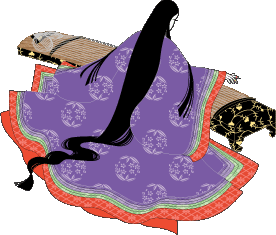源氏物語の「明石」を歩く
光源氏27歳。須磨での暴風雨は止まず、住吉の神や仏に祈り願を立てているところに落雷がありました。その夜、光源氏の夢枕に父である桐壺院が現れ「住吉の神のお導きのままに、須磨の浦を立ち去りなさい」と諭されます。
翌朝、隣国の播磨国から明石の入道が舟で光源氏を迎えに訪れ、光源氏は明石の入道の住まい「浜の館」へ移住するのでした。
こうして物語の舞台は須磨(摂津国)から明石(播磨国)へ、畿内から畿外へと移ります。
※住吉の神=住吉大社(大阪市住吉区)の祭神
明石の入道は富裕な財産を有し、光源氏を厚遇します。
やがて明石の入道は、娘である明石の君と光源氏との結婚をほのめかします。明石の入道は琵琶と筝の琴にすぐれており、娘の明石の君もまた楽器にすぐれ醍醐天皇の奏法に似ていると聞かされた光源氏は、明石の君に関心を惹かれるのでした。
光源氏は「岡辺の家」に住まう明石の君に文を贈り、8月13日に結ばれます。
翌年、朱雀帝から帰京するようにとの宣旨が下った頃、明石の君は懐妊。光源氏はいずれ必ず、明石の君を京に迎えることを誓い帰京します。光源氏28歳のことでした。
■『源氏物語』では、光源氏が「明石」の月を見ながら、京の二條院に残した紫の上を想う場面が描かれています。
 『源氏物語』第13帖<明石>において、望郷の思いで初夏の夕月夜を眺める光源氏。 『源氏物語』第13帖<明石>において、望郷の思いで初夏の夕月夜を眺める光源氏。
のどやかなる夕月夜に、海の上曇りなく見えわたれるも、住み馴れたまひし故郷の池水、思ひまがへられたまふに、言はむかたなく恋しきこと、何方となく行方なき心地したまひて、ただ目の前に見やらるるは、淡路島なりけり。
(訳:のんびりとした夕月夜の晩に、海上に雲もなくはるかに見渡されるのが、お住みなれたお邸(=二条院)の池の水のように、思わず見間違えられなさると、何とも言いようなく恋しい気持ちは、どこへともなくさすらって行く気がなさって、ただ目の前に見やられるのは、淡路島なのであった。)
光源氏は淡路島を見て和歌を詠みます。
「あはと見る淡路の島のあはれさへ
残るくまなく澄める夜の月」
(訳:ああと、しみじみ眺める淡路島の悲しい情趣まで
すっかり照らしだす今宵の月であることよ。)
 |
| 柿本神社前から撮影した明石海峡大橋と淡路島 |
 『源氏物語』第13帖<明石>において、光源氏は、八月十三夜に明石の君が住む「岡辺の家」に招かれます。 『源氏物語』第13帖<明石>において、光源氏は、八月十三夜に明石の君が住む「岡辺の家」に招かれます。
しかし、光源氏の心に浮かぶのはただひとり、京に残した紫の上の面影でした。
思ふどち見まほしき入江の月影にも、まづ恋しき人の御ことを思ひ出できこえたまふに、やがて馬引き過ぎて、赴きぬべく思す。
(訳:恋人同士で眺めたい入江の月影を見るにつけても、まずは恋しい人(=紫の上)の御ことをお思い出し申さずにはいらっしゃれないので、そのまま馬で通り過ぎて、上京してしまいたく思われなさる。)
光源氏は思わず独り言を漏らしました。
「秋の夜の月毛の駒よ我が恋ふる
雲居を翔れ時の間も見む」
(訳:秋の夜の月毛の駒よ、わが恋する都へ天翔っておくれ
束の間でもあの人(=紫の上)に会いたいので)
【源氏物語の本文と訳は 渋谷栄一先生のwebサイト『源氏物語の世界』より引用】
明石の入道は、大臣家の生まれでありながら近衛中将の身分を捨て、播磨守(はりまのかみ)となりました。→右の系図をクリック!
京から離れ、播磨国に土着し蓄財に励んだのも、娘である明石の君を都の貴人と結婚させたいと神仏に願ってきたから・・・。
光源氏を明石に迎え、一族繁栄の実現が近づく機会と考えます。
明石の入道と光源氏をひきあわせたのは、住吉の神なのでした。 |
|
「明石」は、「明かし(あかし)」<形容詞>に通じることから考えてみます。(*^-^)b
「明く(あく)」<動詞>が形容詞化したものが「明かし」ですが、「明く」には、夜または年が明ける、ある期間またはある状態が終わって、次の期間・状態になるという意味があります。
「明かし」(形容詞)には、明るいという意味のほか、心に曇りがないという意味もあります。
『源氏物語』において「明石(あかし)」の地名と呼応するかのように、光源氏の人生も陰から陽へ、明るい将来に向けての燈火が見えてきます。
そして、光源氏は朱雀帝の宣旨により、“心に曇りなく”帰京を果たします。
■柿本人麻呂の歌(古今和歌集・巻九)
ほのぼのと明石の浦の朝霧に
島隠れ行く舟をしぞ思ふ
(訳:ほのぼのと夜が明けていく明石の浦の朝霧の中を行く舟が
島影に隠れて行くのを私はしみじみとした思いで見つめています。)
■柿本人麻呂の歌をふまえて、帰京した光源氏は明石の君へ以下のような歌を贈っています。
「波のよるよるいかに、
嘆きつつ明石の浦に朝霧の
立つやと人を思ひやるかな」
(訳:「波の寄せる夜々は、どのように、
お嘆きになりながら暮らしていらっしゃる明石の浦に
嘆きの息が朝霧となって立ちこめているのではないかと想像しています」)
【源氏物語の本文と訳は 渋谷栄一先生のwebサイト『源氏物語の世界』より引用】
現在も、明石海峡と霧は切っても切れない縁のようです。
海面がみえないほど霧がたちこめるのですね。(°O°;)
▲このページの一番上に戻る
|